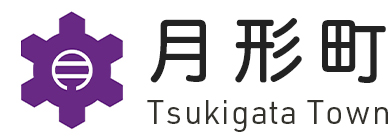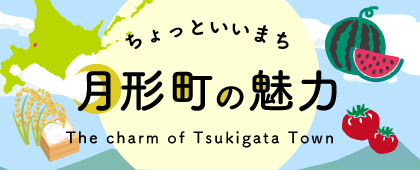本文
月形町内の建築規制について
建築基準法に関するよくあるお問い合わせ
Q & A
Q 1.月形町の都市計画区域はありますか。
A.月形町は人口が1万人以上に満たないため、都市計画区域の対象外となります。
◇そもそも都市計画区域とは?
都市計画法第5条(都市計画区域)
都道府県は、市または人口就業者数その他の事項が政令で定める要件に該当する市街地を中心に、一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区域を都市計画区域といいます。
◇政令で定める要件とは?
都市計画法施行令第2項第2条(都市計画区域に係る町村の要件)
- 人口が1万人以上かつ、商工業その他の都市的業態に従事する者の数が全就業者数の50%以上であること。
- 町村の発展状況、人口及び産業の見通し等からみて、おおよそ10年以内に一号に該当すると認められること。
- 町村の中心市街地が3,000人以上であること。
- 観光資源により多数人が集中するため、良好な都市環境の形成を図る必要があること。
- 火災、震災などで町村を形成している建築物の相当数が減失した場合。
Q 2.月形町の用途地域はありますか。
A.用途地域は、都市計画区域に該当する市町村にしか適用されないため、そもそも都市計画区域外である月形町には適用されません。
◇そもそも用途地域とは?
建築基準法第48条(用途地域等)
市街地の各地区に最も適した類似の用途の建築物を集め、同時にその地区にふさわしくない用途ものを排除して、都市の総合的な発展を図るものです。住居系、商業系、工業系等用途地域は現在12種類あります。
Q 3.適用される規定にはどのようなものがありますか。
A.単体規定(建築基準法第19条~第41条)は個々の建築物が満たすべき基準で全国の建築物全てに対して適用され、単体規定では主に(1)敷地、(2)構造、(3)防火・避難、(4)衛生等について定められています。
◇単体規定抜粋(建築基準法第19条~第41条)
(1)敷地
建築物の敷地は、接する道の境よりも高くなければならず、また地盤面は接する周囲の土地より高くなければなりません。ただし、敷地内の排水に支障がない場合や、建築物の用途により防湿の必要がない場合は、この限りではありません。
建築物の敷地には、雨水及び汚水を排出し、又は処理するための適当な下水管、下水溝これらに類する施設を設けなければなりません。
(2)構造
建築物は、様々な重さ、圧力、地震等の振動、衝撃に耐えられる安全な構造のものとし、また床屋根・階段を除いた主要構造部(=壁・柱・梁)に木材やプラスチック等の燃えやすい素材を用いた建築物で、
「高さが13m超又は軒の高さが9m超の建築物」
「延べ面積3,000平方メートル超の建築物」
のいずれかに該当する建築物は、
- 耐火構造であること。
- 火災についての性能に関する一定の技術的基準を満たしていること。
のどちらかに適合する必要があります。
(3)防火・避難
【大規模の木造建築物等の外壁など】
延べ面積(同一敷地内に2つ以上の木造建築物がある場合は延べ面積の合計)が1,000平方メートル超の木造建築物等は、外壁及び軒裏で延焼のおそれがある部分を耐火構造としなければなりません。また、屋根の構造についても火災に対する性能が政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法あるいは、認定を受けたものとしなければなりません。
【防火壁】
延べ面積1,000平方メートル超の建築物(耐火建築物又は準耐火建築物等を除く)は、防火上有効な構造の防火壁によって有効に区画し、各区画の床面積の合計をそれぞれ1,000平方メートル以内にしなければなりません。
【建築設備】
-
避雷設備:高さ20mを超える建築物は、有効に避雷設備を設けなければなりません。ただし、周囲の状況によって安全上問題がなければ、避雷設備を設けなくてもよいとされています。
- 非常用昇降機:高さ31mを超える建築物には、非常用の昇降機を設けなければなりません。
(4)衛生
【居室の採光及び換気】
- 採光:住宅の居室、学校の居室、病院の病室等には、採光のための一定面積の窓その他開口部を設けなければなりません。
住宅の場合→ 居室の床面積 × 7分の1 以上
住宅以外の場合→ 居室の床面積 × 政令で定める一定の割合(5分の1 から 10分の1)以上 - 換気:居室には、換気のための一定面積の窓その他の開口部を設けなければなりません。
居室の床面積 × 20分の1 以上
【石綿等の飛散・発散に対する衛生上の措置】
石綿(アスベスト)その他の物質の建築材料からの飛散・発散による衛生上の支障がないように、次に掲げる基準に適合するものでなければなりません。
- 建築材料に石綿等を添付しないこと。
- 石綿等をあらかじめ添付した建築材料を使用しないこと。
- 居室を有する建築物では、上記の他、石綿等以外の物質で居室内において衛生上の支障を生ずるおそれのあるもの、政令で定める物質(クロルピリホス、ホルムアルデヒド)の区分に応じて建築材料及び換気設備について政令で定める技術的基準に適合するものでなければなりません。
【地階における住宅等の居室】
住宅の居室、学校の教室、病院の病室で地階を設けるものは、壁及び床の防湿の措置その他の事項について、政令で定める技術的基準に適合するものとしなければなりません。
【便所】
下水道法に規定する処理区域内において便所は、水洗便所以外の便所としてはいけません。
Q 4.月形町の凍結深度は何cmですか。
A.月形町の凍結深度は80cmとなっています。
◇そもそも凍結深度とは?
冬場に気温が0度以下に下がるような寒冷地では、地表から一定の深さまで凍結します。この凍結するラインを「凍結深度」といいます。この凍結深度は地域によって深さが変わり、地面が凍結すると膨張して地盤が押し広げられるため、建築物の基礎や、水道本管からの横引き給水管は、凍結深度より深い位置に設置する必要があります。
Q 5.確認申請が必要な建築物には何がありますか。
A.該当する建築物については下記のとおりです。
◇建築基準法第6条(建築物の建築等に関する申請及び確認)
(1)法別表1(い)欄に記載のある特殊建築物で床面積の合計が200平方メートル以上の場合
法別表1(い)欄抜粋
- 劇場、映画館等
- 病院、ホテル、共同住宅等
- 学校、体育館等
- 百貨店、マーケット、カフェ等
- 倉庫等
- 自転車車庫、自動車修理工場等
これらに類する建築物
(2)特殊建築物又はそれに類する建築物以外の建築物で下記のいずれかに該当するもの
- 階数が2以上のもの
- 延べ床面積が200平方メートル以上のもの
※ 確認申請とは別に建築物省エネ法の改正(令和7年4月1日施行)により令和7年4月1日以降に工事着手する全ての住宅・建築物の新築・増改築について、省エネ基準への適合が義務付けられます。(確認申請が不要な建築物については省エネ基準の適合性審査も不要です。)
Q 6.容積率と建ぺい率の制限はありますか。
A.都市計画区域内における「用途地域の指定のない区域」を準用して容積率400%以下、建ぺい率70%以下でお願いしております。
ただし、月形町は都市計画区域外のため上記の制限に法的根拠はありません。
◇そもそも容積率と建ぺい率とは?
容積率:敷地面積に対する建物各階床面積の合計(延べ床面積)の割合。
建ぺい率:建物の敷地面積のうち、建物が建っている部分の面積(建築面積)の割合。