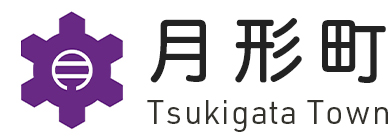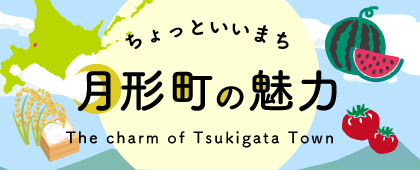本文
葬祭費
高額療養費支給制度
高額療養費とは
医療費の一部負担金が高額になったとき、申請をして認められた場合、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
70歳未満の自己負担限度額(月額)
| 所得要件※ | 限度額 |
|---|---|
|
【ア】旧ただし書き所得 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% |
|
【イ】旧ただし書き所得 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% |
|
【ウ】旧ただし書き所得 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% |
|
【エ】旧ただし書き所得 |
57,600円 |
| 【オ】住民税非課税世帯 |
35,400円 |
- 旧ただし書き所得とは、総所得金額から基礎控除(33万円)を引いた所得をいいます。
※所得要件の【ア】~【オ】は「認定証」に記載される区分を示しています。
所得の申告をしていない人も区分【ア】とみなされます。
70歳未満の人の自己負担額の計算のしかた
- 月の1日から末日まで、暦月ごとの受診について計算します。
- 2つ以上の医療機関にかかった場合は、別々に計算します。
- 同じ医療機関の場合でも、歯科は別計算になります。
また、外来・入院も別計算になります。 - 入院時の食事代や保険がきかない差額ベッド料などは、支給の対象外です。
70歳以上の高齢受給者証対象者の自己負担限度額(月額)
| 所得要件 |
限度額 |
限度額 |
|
|---|---|---|---|
| 現役並み所得者3 |
課税所得 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% |
同左 |
| 現役並み所得者2 |
課税所得 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% |
同左 |
| 現役並み所得者1 | 課税所得 145万円以上 380万円未満 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% |
同左 |
| 一般 |
課税所得 |
18,000円 |
57,600円 |
| 低所得2 | 住民税非課税 | 8,000円 | 24,600円 |
| 低所得1 |
住民税非課税 |
8,000円 | 15,000円 |
-
現役並み所得者
同一世帯に一定以上(課税所得145万円以上かつ収入383万円以上、2人以上の場合は収入520万円以上)の所得がある70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる方 -
一般
収入の合計金額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合及び旧ただし書き所得の合計が210万円以下の方 -
低所得者2
同一世帯の世帯主と全ての国保被保険者が住民税非課税である方 -
低所得者1
同一世帯の世帯主と全ての国保被保険者が住民税非課税であって、その世帯の所得が一定基準以下の方
70歳以上の人の自己負担限度額の計算のしかた
- 月の1日から末日まで、暦月ごとの受診について計算します。
- 外来は個人ごとにまとめますが、入院を含む自己負担限度額は世帯で合算します。
- 病院・診療所、歯科の区別はありません。また、調剤薬局の自己負担額も合算します。
- 入院時の食事代や保険がきかない差額ベッド料などは、支給の対象外です。
- 合算対象基準…同一世帯で同一月、同一医療機関の診療科で、それぞれが21,000円を超えている場合、合算することができます(ただし、入院と通院分の金額は別計算)。また70歳以上の高齢受給者(後期高齢者医療被保険者を除く)と70歳未満の方が同じ世帯の場合は合算できる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
※血友病の方、および人工透析を受けている慢性腎不全の方等の場合
申請により交付される「特定疾病療養受領証」を提示すれば、一つの医療機関での1か月の自己負担は1万円までとなります。該当する方は、その事実を証明する書類(医師の意見書など)、国民健康保険証、印かんをお持ちになって申請してください。
申請の方法
申請に必要なもの
領収書、国民健康保険証と世帯主の印かん、世帯主の預金口座のわかるもの
※高額療養費は、医療機関から送付される「診療報酬明細書(レセプト)」に基き支給を行うため、保険者への送付が遅れている場合は、支払いが遅くなることがあります。ご了承ください。
※診療月の翌月1日から原則2年で時効となり、申請ができなくなりますのでご注意ください。
限度額適用認定証
70歳未満の方及び、70歳~74歳の非課税世帯の方が入院するときに、医療機関の窓口で「限度額適用認定証」を提示することで、窓口での医療費の支払いが限度額までの支払となります。
町民税非課税世帯の方には、入院時の食事代も減額となる「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付します。
※保険税を滞納している世帯には原則、交付されません。
申請に必要なもの
国民健康保険証、世帯主の印かん
高額介護合算療養費
高額介護合算療養費とは
同じ世帯で、国民健康保険と介護保険の自己負担額の合計が、次の表の限度額を超えた場合、申請により超えた額が払い戻しされます。
計算は、毎年8月から翌年7月までの1年間で行い、翌年8月から申請を受け付けます。
70歳未満の人(年額/8月~翌年7月)
|
所得区分 |
自己負担限度額 |
|---|---|
|
一般 |
67万円 |
|
上位所得者 |
126万円 |
|
住民税非課税世帯 |
34万円 |
70歳以上75歳未満の人(年額/8月~翌年7月)
|
所得区分 |
自己負担限度額 |
|---|---|
|
一般 |
56万円 |
|
現役並み所得者 |
67万円 |
|
低所得者2 |
31万円 |
|
低所得1 |
19万円 |
申請に必要なもの
- 国民健康保険証
- 世帯主の印かん
- 世帯主の預金口座のわかるもの
療養費の支給
療養費の支給が受けられる場合
やむを得ない理由、例えば旅行先などで病気やケガをして国民健康保険証を持っていなかったときは、本人が医療費の全額を支払うことになります。このような場合、申請して認められた場合には、保険診療の範囲内で一部負担金を差し引いた額が支給されます。
療養費の支給例
| ケース | 申請に必要なもの | |
|---|---|---|
| やむをえない理由で医療費を全額自己負担した場合 |
|
|
| コルセットなど治療用装具を作った場合 |
|
|
| ※その他にも払い戻しが受けられる場合があります。 | ||
様式
国民健康保険療養費支給申請書(申請書ダウンロード8番)
入院時食事療養費
入院時食事療養費
国保加入者が入院した場合(療養病床に入院する65歳以上の人を除く)、食事代として1食490円は自己負担となります。これを食事療養標準負担額といい、食事療養標準負担額を超えた額は国民健康保険が負担します。住民税非課税世帯の方は、申請により交付される「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示することで、下記の負担額になります。
入院時の食事に係る標準負担額
70歳未満の方の入院時食事療養標準負担
| 区分 | 食事代(1食あたり) |
|---|---|
| 一般(住民税課税世帯) | 490円(※2) |
| 住民税非課税世帯(過去12か月の入院日数90日以下)(※1) | 230円 |
|
住民税非課税世帯(過去12か月の入院日数91日以上) 長期入院該当(※1) |
180円 |
70歳以上の方の入院時食事療養標準負担
| 区分 | 食事代(1食あたり) |
|---|---|
| 現役並み所得者、一般(住民税課税世帯) | 490円(※2) |
| 低所得者2(過去12か月の入院日数90日以下)(※1) | 230円 |
| 低所得者2(過去12か月の入院日数91日以上)長期入院該当(※1) | 180円 |
| 低所得者1(世帯主及び国保加入者全員が所得0円(年金を受給している方は年金収入80万円以下)の世帯) | 110円 |
※1:世帯主及び国保加入者全員が住民税非課税である世帯に属する方の区分です。入院月が1月から7月の場合は前々年の収入から計算された住民税、8月から12月の場合は前年の収入から計算された住民税により区分判定が行なわれます。なお、所得の確認ができない方(未申告の方)が世帯にいる場合はこの区分となりません。
※2:指定難病の方や小児慢性特定疾病の方等は280円となります。
長期入院該当について
住民税非課税世帯の方で、限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を既に受けている方が、過去12ヶ月の入院日数が90日を超えた場合は、長期入院該当認定の申請をすることで1食あたりの負担額がさらに減額されます。
入院日数は、長期該当認定の申請月を含めた過去12カ月間の入院日数の合計で計算します。ただし、過去12カ月間の入院日数は、限度額適用・標準負担額減額認定証を発行している期間中で日数計算をします。長期該当の適用は原則申請月の翌月初日からとなります。申請月から長期該当適用日までの間に入院があり、食事代を長期該当適用前の金額で支払った場合は、申請により差額を支給します。差額の支給については、下記の「標準負担額減額差額支給」をご参照ください。
申請に必要なもの
- 長期該当認定を受ける方の保険証
- 既に交付されている限度額適用・標準負担額減額認定証
- 入院日数が90日を超えていることが確認できる書類(領収書など)
- 世帯主及び長期該当認定を受ける方の個人番号を確認できるもの
※世帯主以外の方が手続きをされる場合は、印鑑(シャチハタ以外)も併せてご持参ください。
個人番号の確認書類について
マイナンバーカード、通知カード(氏名、住所等の記載事項に変更がない場合に限ります。)、個人番号が記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書
限度額適用・標準負担額減額認定証の交付
申請に必要なもの
- 国民健康保険証、世帯主の印かん
※過去1年間に91日以上入院している方は「病院の領収書」など91日以上入院していることが確認できるものをお持ちください。
標準負担額差額支給
やむを得ず減額認定証の提示ができず、通常の費用を支払ったときは申請に基づき,差額を支給します。
申請に必要なもの
- 国民健康保険証
- 世帯主の印かん
- 領収書
- 世帯主の預金口座のわかるもの
様式
国民健康保険食事療養標準負担額減額認定証交付申請書(申請書ダウンロード10番)
国民健康保険食事療養標準負担額差額支給申請書(申請書ダウンロード9番)
訪問看護療養費
訪問看護療養費
難病患者や重度の障害のある方が、主治医の指示のもとで訪問看護ステーションを利用した場合、利用料を支払うだけで残りは「訪問看護療養費」として国保が負担します。
なお、訪問診療に要した交通費は実費負担となります。また、訪問看護ステーションを利用する場合は国民健康保険証の提示が必要です。
移送費
移送費の支給
緊急やむを得ない理由で、医師の指示により移動が困難な重病人を自動車等で入院、転院させたとき、必要であると認められた場合移送に要した費用が支給されます。ただし、通院に使用した場合は対象になりません。
※費用を支払ってから2年を過ぎますと時効により、申請ができなくなりますのでご注意ください。
申請に必要なもの
- 国民健康保険証
- 世帯主の印かん
- 世帯主の預金口座のわかるもの
- 移送を必要とする医師の意見書 (移送を認めた理由、付き添いがあった場合はその付き添いを必要とした理由、移送経路・移送方法及び移送年月日の記載のあるもの)
- 移送にかかった費用の領収書 (移送区間・距離のわかるもの)
特別療養費
特別療養費
災害などの特別の事情がないにもかかわらず、長期にわたって保険料を滞納している世帯主に対して、保険証の返還を求めた上で、これに代わる被保険者資格証明書(以下、「資格証明書」という)を交付することがあります。
資格証明書を交付された方が、医療機関で療養の給付等を受けた場合は、その費用を全額支払い、一部負担金相当額を除いた額が、「特別療養費」として支給されます。
申請に必要なもの
資格証明書、領収書、世帯主の印かんなど
出産育児一時金
出産育児一時金
国民健康保険の加入者が出産したとき、世帯主に出産育児一時金が支給されます。
支給額
42万円
申請に必要なもの
- 国民健康保険証
- 世帯主の印かん
- 母子手帳(死産・流産の場合は医師の証明書)
葬祭費
葬祭費の支給
国民健康保険の加入者が死亡したとき、その葬祭を行った方(喪主)に葬祭費が支給されます。
支給額
2万円
申請に必要なもの
- 保険証
- 葬祭を行った者(喪主)の印かん
国民健康保険の給付制限
交通事故、仕事上のけがや病気にはご注意を
交通事故などで第三者から傷害を受けた場合でも、国保を使って治療を受けることができます。ただし、治療費は加害者が全額負担するのが原則です。したがって国保が一時立替をし、後で加害者へ請求することになりますので、事故にあったときはすぐに国保の窓口へ届け出てください。
仕事上のけがや病気の場合は、労災保険が適用されるか、労働基準法に従って雇主の負担となります。
国民健康保険の給付制限
国民健康保険に加入していても、次のような場合には給付が受けられなかったり、制限されることがあります。
| 給付が受けられないもの (保険診療外のもの) |
制限されるもの |
|---|---|
|
など |