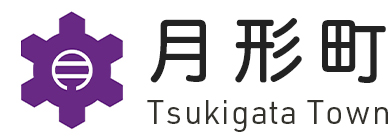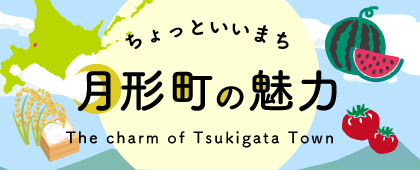本文
国民健康保険制度について
国民健康保険制度について
国民健康保険とは
日本では、すべての国民が何らかの健康保険に加入することになっており、これを国民皆保険制度といいます。
国民健康保険は、職場の健康保険に加入している人や、生活保護を受けている方以外は、すべての方が加入することになります。また、加入者全員が保険税を納付し、医療費を負担し合う助け合いの制度です。加入者の皆さんが病院にかかった医療費のうち、自己負担分を除く費用は国民健康保険が負担しています。
国民健康保険の加入資格
月形町に住んでいる74歳以下の方は、国保以外の公的医療保険(協会けんぽ、共済組合など)を除き、すべて国保に加入しなければなりません。
国民健康保険に加入できない方
国保以外の公的医療保険加入者又は他の法律が適用される方は国保に加入できません。
- 勤務先の健康保険に加入されている方及びその扶養者
- 各種共済組合に加入している方及びその扶養者
- 国民健康保険組合に加入している方及びその家族
- 後期高齢者医療保険に加入している方
- 生活保護を受けている方 など
令和6年12月2日以降の国民健康保険証の取扱いについて
令和6年12月2日から国民健康保険証の新規発行が終了し、保険証利用登録がされたマイナンバーカード(マイナ保険証)を基本とする仕組みに移行しました。マイナ保険証をお持ちの方は、原則マイナ保険証を持参して医療機関等を受診することになりますが、特別な事情によりマイナ保険証で医療機関等を受診することが困難な場合、申請していただくことで資格確認書を交付します。
資格確認書とは
資格確認書とは、保険証利用登録がされたマイナンバーカード(マイナ保険証) を持たない人や、特別な事情によりマイナ保険証で医療機関等を受診することが困難な人が、保険診療を受けられるように発行されるものです(カード型)。交付された資格確認書は手元に保管し、紛失しないように注意してください。医療機関等で資格確認書を提示することで、一定の負担割合で受診できます。 資格確認書の有効期限は毎年7月31日です。マイナ保険証をお持ちでない方には、新しい資格確認書を7月下旬頃に郵送します。更新手続きは不要です。
なお、有効期限に至った資格確認書は、次の点に気を付けて被保険者自身で破棄してください。
・誤使用を防ぐため、個人情報に留意の上、被保険者自身で裁断する等、確実に破棄すること。
・有効期限を経過したときは、資格確認書を使用することができないこと。
・有効期限が経過した資格確認書を使用して保険給付を受けた場合は、保険給付費の返還を求める場合があること。
資格確認情報のお知らせ(資格情報通知書)とは
資格情報のお知らせ(資格情報通知書)とは、保険証利用登録がされたマイナンバーカード(マイナ保険証) をお持ちの方が、自身の被保険者資格等を簡易に把握できるように発行されるものです。なお、資格情報のお知らせ(資格情報通知書)のみでは医療機関等を受診できません。受診の際は、マイナンバーカードをご持参ください。資格情報のお知らせ(資格情報通知書)を紛失・汚損等された場合でも、マイナポータルの健康保険資格情報画面でご自身の資格情報を確認できる場合は、再通知の必要はありません。
これから70歳になる国保被保険者の方へ
70歳から74歳の国保被保険者には、70歳になる月の下旬(1日生まれの方は前月下旬)に負担割合の記載された資格確認書又は資格情報のお知らせ(資格情報通知書)を郵送します。負担割合が適用になるのは、70歳の誕生月の翌月(1日生まれの方は誕生月)からとなります。負担割合の判定については、下記の「一部負担金の割合(医療機関での窓口負担)について」をご確認ください。
一部負担金の割合(医療機関での窓口負担)について
| 年齢 | 負担割合 | ||
|---|---|---|---|
| 義務教育就学前 | 2割 | ||
| 義務教育就学以上70歳未満 | 3割 | ||
| 70歳以上(兼高齢受給者証) | 2割(一定の所得がある方(現役並所得者)は3割) | ||
70歳以上の一部負担金(医療機関での窓口負担)の割合の判定は、毎年8月に前年の所得に基づき行います。
次の場合は、負担割合は2割になります。
- 70歳から74歳の国保被保険者の町民税の課税標準額が145万円未満の場合。
- 70歳から74歳の国保被保険者の政令で定める所得の合計額が210万円以下の場合。
上記1、上記2いずれかに該当しない場合、負担割合は3割になります。
また、上記1、上記2どちらにも該当しない場合でも、次のいずれかに該当する場合は、申請により一部負担金の割合が2割となります。
- 70歳から74歳の国保被保険者が1人いる世帯で、前年中の収入金額が383万円未満の場合、または70歳から74歳の国保被保険者が2人以上いる世帯で、前年中の収入金額が520万円未満の場合。
- 70歳から74歳の国保被保険者が1人いる世帯で、前年中の収入金額が383万円以上あるが、世帯の中に、国保から後期高齢者医療の被保険者に移られた方がいて、その方との合計収入金額が520万円未満の場合。